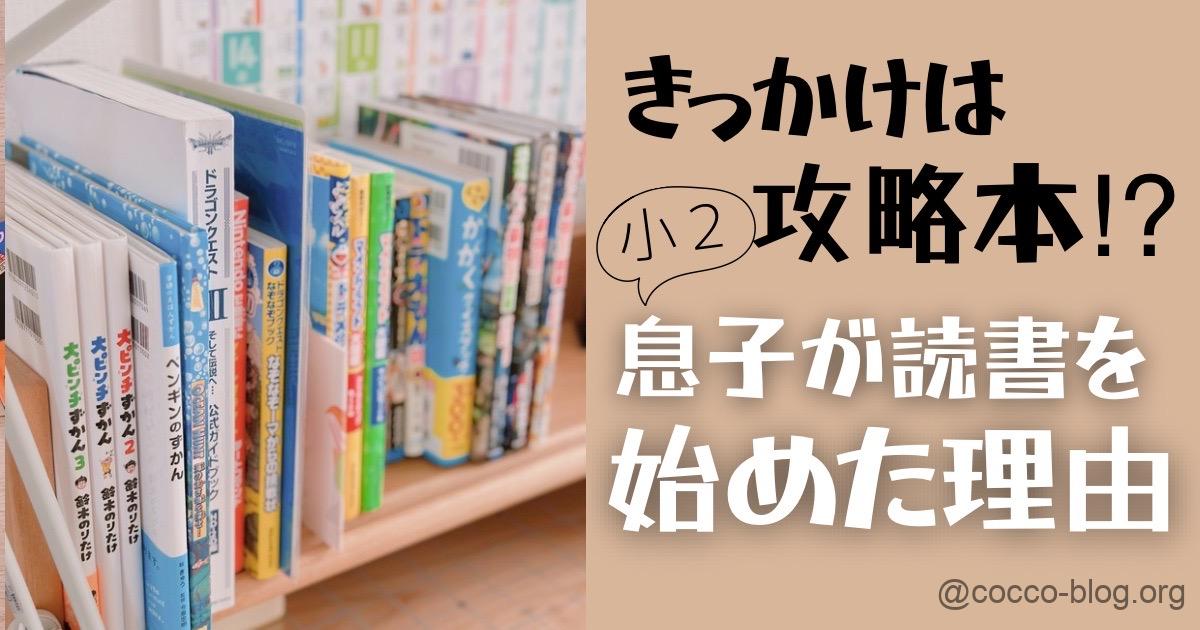将来、本を読む子に育ってほしい。
特別に教育熱心な家庭でなくても、多くの親御さんが一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか。
実際、「本を読む子の方が学力が高い」というデータもありますし、幼少期からの読み聞かせが大切だということも、いまや広く知られていますよね。
だからこそ私も、眠い目をこすりながらできるだけ寝る前に読み聞かせを続けました。
そうすれば、小学生になる頃には自然と自分で読むようになるだろうと信じていたのです。
ところが、待てど暮らせどその気配はなし。
「何が間違っていたんだろう?」と悩んだこともあります。
そんなときに突破口になったのは、なんと ゲームの攻略本。
そこから息子の読書スタイル、そして私自身の考え方も大きく変わっていきました。
そこでこの記事では、息子と私の体験をふり返りつつ「子どもが自分で本を読むようになるきっかけ」についてまとめています。
同じように悩んでいる親御さんの参考になれば嬉しいです。
小学生は“読書習慣”の分かれ道?
そもそもなぜ子どもに読書習慣をつけたいのか──
それは「読書は子どもの成績や学力と強く関係している」という調査結果が数多く出ているからではないでしょうか。
以下のようなデータも、読書のメリットを物語っています。
- 文部科学省「全国学力・学習状況調査」では、本を読む子どもほど国語や算数の正答率が高い傾向がある。
- 「ベネッセ教育総合研究所」の調査では、小学生のうちに毎日読書していた子は、中学生以降も学習習慣が安定しやすい。
- 「国立青少年教育振興機構」の調査では、読書量が多い子どもほど「自己肯定感」や「コミュニケーション力」も高い。
一方で、小学生になると読書時間は年々減っていく傾向があります。
理由のひとつは、低学年になると「もう小学生だし…」となんとなく読み聞かせをやめてしまう家庭が多いから。
もうひとつは、高学年や中学生になるにつれて、SNSやゲーム、動画などに時間を奪われ、本に触れる機会が減るからです。
つまり、小学生のうちに読書をゲームや動画やSNSに負けない“遊びの選択肢のひとつ”として加えられるかどうかが、その後の読書習慣の分かれ道になるのではないかと考えました。
そこで、息子が小学生になったのを機に名作と言われる児童書を用意してみたのですが……現実は思うようにいかず。
でもそこから大きな気づきがありました。次の章ではそのお話をしていきます。
ゲームの攻略本が読書の入り口に
息子が小学生になったのを機に、そろそろ絵本から児童書へ移行させようと、名作や評判のよい児童書を用意して、まずは読み聞かせから始めてみることにしました。
ところが、どの本も全く興味を示さない。それどころか退屈そうにあくびを噛み殺し、最終的には「こっちを読んで」と絵本を持ってくる始末…。
ただ、その頃から息子に小さな変化がありました。
「俺はこの2冊を読むから、ママはそっちの3冊を読んで」と、私に絵本を読み聞かせしてくれるようになったのです。
また別の日には、ケンカをした後あまりにも静かな息子を心配して部屋を覗いてみると、絵本を何十冊も引っ張り出して1人で読んでいました。
絵本ではあるものの、自分の意思で読もうとする姿は印象的で、このとき初めて息子は「読めない・読みたくないわけじゃなく、きっかけさえあれば読むんだ」と気づきました。
そこで試しに、当時夢中になっていたドラゴンクエスト3の攻略本を買い与えてみることに。
分厚くて文字も小さく絵本とは全く違うのでちょっとしたチャレンジでしたが、これが狙いどおりの大ヒット!
最初はゲームでわからない部分を調べていただけなのに、そのうちゲームをしていないときまで読み込むようになり、最終的には詰め込んだ知識でクイズを出題するというアウトプットまで披露するようになりました。
「攻略本でもいいんだ!」
児童書や図鑑にハマらなくても、子どもの興味のある分野から入れば“自分で読む楽しさ”を見つけられる。
それは、私の中で読書への考え方が大きく変わった瞬間でした。
読む本より大事なのは“習慣”
攻略本に夢中になる息子を見て気づいたこと。
それは「何を読むか」よりも「読む習慣があるか」の方が大切なのではないかということでした。
私も最初は「年齢に相応しい児童書を読むこと」「図鑑から興味の幅を広げること」──そういう理想的な読書をしてほしいと思っていました。
でも実際は、興味のない本を与えても、全く響かないんですよね…。
それよりも、自分の好きなことに関連した本なら、どんどん読み進めていく。
実際に息子もドラゴンクエストの攻略本からマイクラの攻略本、鬼滅の刃のファンブック、そして今は最強図鑑にハマっています。
読書=勉強や努力ではなく、遊びの選択肢のひとつとして自然にそこにあること。
「暇だからゲーム」「暇だからYouTube」と同じように、「暇だから本を読む」という選択肢が増えれば十分意味があると実感しました。
この考えをさらに確信に変えてくれたのが、笹沼颯太さんの著書『ハマるおうち読書』です。
笹沼さんは、子ども達に読書の楽しさを伝えるために Yondemy(ヨンデミー)というサービスを立ち上げ、その子に合った本の選び方や読み方を“習い事”として提供するという新しい取り組みをされています。
本の内容も「好きな本からでいい」「無理に読ませなくてもいい」といった考え方が軸になっていて、冒頭から首がもげるほど頷きながら読みました。
▼興味のある方はぜひ読んでみてください
まとめ|読書は好きな本から習慣へ
息子の体験を通して改めて感じたのは、「きっかけさえあれば読書習慣は育つ」ということでした。
児童書や図鑑にハマらなくても、攻略本やファンブックでもいい。
そこから「自分で読む楽しさ」に出会えれば、それが大きな第一歩だと思います。
いまでは息子にとって、読書は「暇つぶしの選択肢のひとつ」になりました。
正直まだ「ゲーム」「YouTube」と並ぶまではいきません。
それでも「本を読む」という選択肢が自然にそこにある――それが何より嬉しい変化です。
親ができるのは、押しつけることではなく、子どもの“今の興味”に合った本をそっと用意して、環境を整えること。
それが、読書を長く続けるための一番のサポートだと思います。
前章でも紹介した『ハマるおうち読書』(笹沼颯太 著)の冒頭に私が強く共感したこんな言葉があります。
“きみが歩く道の先には うれしいこともあるだろう つらいこともあるだろう いつでもそばで喜びをわかちあいたい 困ったときにはすぐに手をさしのべたいけれど きっとそんなわけにもいかない だからきみには伝えたい 本を読む力を 本はいつでもきみの近くにいてくれる どんなときにも言葉をくれる パワーをくれる 今を生きるきみの味方でいてくれる”
親はいつまでも子どものそばにいられるわけではありません。
だからこそ「本」という味方がいてくれたら、とても心強いと思うのです。
わが家では攻略本がきっかけになりましたが、「うちの子に合った本って何だろう?」と悩む方には、子ども専用の読書習い事サービス ヨンデミー を試してみるのもおすすめです。
私も体験しましたが、AI先生が子どもの興味やレベルに合わせて本を提案してくれるので、「そうきたか!」という意外な出会いがありました。
▼ヨンデミー公式サイトはこちら

これからも息子に寄り添いながら、本との出会いをサポートしていきたいと思います。
みなさんのお子さんにも「読書」という心強い味方ができますように。