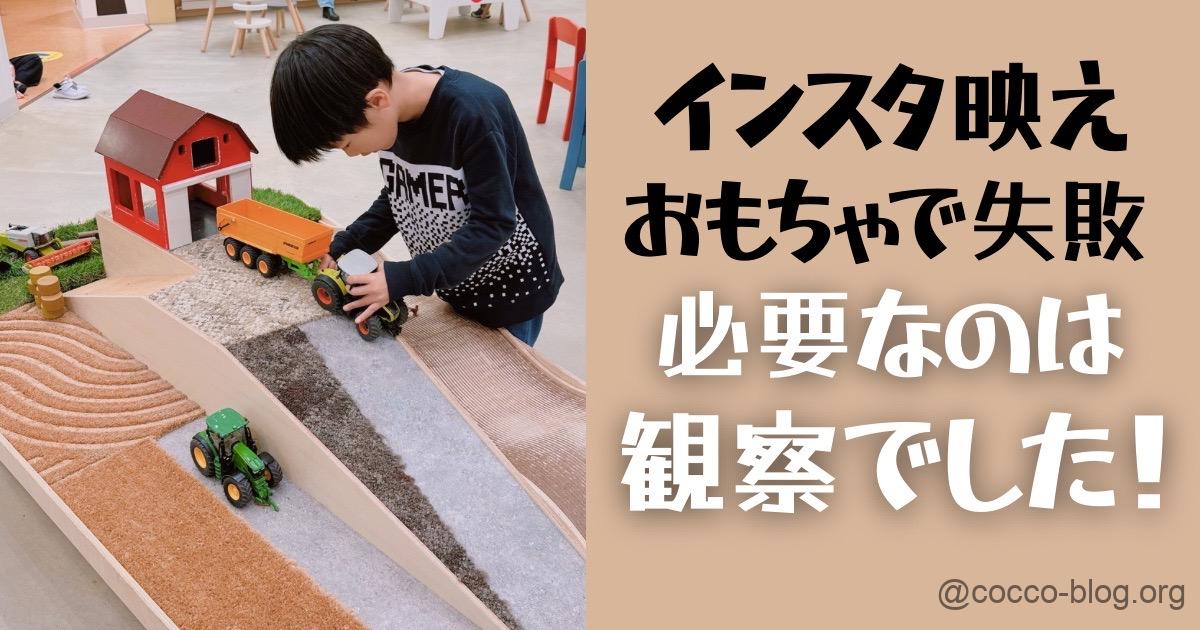数年前、更新を心待ちにして毎日のように読んでいたブログがあった。
カラフルなおもちゃがたくさん並んでいるのに、ごちゃごちゃしていなくて、
子ども部屋はもちろん、家全体が本当に素敵だった。
その方(Mさん)が投稿する写真や言葉には、いつも温かさがあって、
「こういう暮らしがしたいな」「私もこんなふうに子育てしたいな」と、心から思っていた。
特に印象的だったのは、同じ年頃の息子さんが1人遊びを楽しんでいる様子。
たくさんの積み木やおもちゃを上手に使って遊ぶ姿が自然に映っていて、
「きっとおもちゃ選びがうまいんだろうな」って思ったし、
「こんなお部屋だからこそ、子どもものびのび遊べるんだろうな」って感じた。
だから私も、紹介されていたおもちゃを実際にいくつか購入してみたことがある。
おしゃれで、カラフルで、どれも素敵なおもちゃたち。
Mさんのように、遊びと暮らしがなじんだ空間を目指して。
だけど、いざ買ってみると――
息子はほとんど遊ばなかった。数分触っただけで興味をなくして、放置。
「なんで?」「どうしてうちは違うの?」
せっかく揃えたおもちゃたちを前に、正直少しイラだったのを覚えている。
お恥ずかしい話だが、今思うと私は“息子の好きなもの”なんて全然無視して
ただただ憧れのMさんに近づこうとしていた。
「こういう暮らしが正解」って、思い込んでいたんだと思う。
今回は、そんな過去の失敗を振り返りながら、
我が家で本当にハマったおもちゃ・ハマらなかったおもちゃを正直に振り返ってみたいと思う。
もし誰かが「うちの子、あまりおもちゃで遊ばないかも…」と感じたとき、
少しでも気持ちが軽くなったらうれしいな。
理想の育児をするMさんに囚われていた私
具体的なおもちゃ名をあげる前に、なぜ私が”失敗”してしまったのか。
少しだけ、当時の背景を振り返ってみたい。
当時は、ちょうどコロナが蔓延していた頃。
人と会うのも難しくて、家にこもる日々が続いていた。
外遊びもままならず、支援センターも閉まっている。
初めての育児で、右も左もわからない中、
「家でどう遊べばいい?」「この時間の使い方で大丈夫?」
と正解が見えないまま、モヤモヤと時間だけが過ぎていった。
日中は息子のお世話で手一杯。
だから夜、息子が寝てからが唯一の”情報収集タイム”。
寝おちするまでスマホを片手に「1歳 おもちゃ おすすめ」
「一人遊び できない」「知育玩具 効果」など
答えを求めて、ひたすら検索を繰り返していた。
そんなときに出会ったのが、Mさんのブログ(のちにインスタへ移行)。
カラフルなおもちゃに囲まれた、遊びやすそうな子ども部屋。
丁寧すぎず、でも心地よく整えられた暮らし。
そして何より印象的だったのが、Mさんが息子さんと過ごす時間が
自由で、楽しそうで、ゆとりがあるように見えたこと。
「こんなふうに遊べたら…」「こんな子育てが、きっと正解なんだろうな」
そう思わせてくれるだけの説得力があった。
だから、少しでもMさんに近づきたくて、紹介されていたおもちゃを買ってみたし、部屋のつくり方も真似してみた。
でも今になって思う。
それは、自分の価値観ではなく、Mさんの正解に頼ろうとしていたのだと。
本当は、目の前の息子をちゃんと観察することが必要だったのに、
「どうしていいかわからない」から、他人の正解に乗っかって、答えを得ようとしていた。
我が家でハマった/ハマらなかったおもちゃ
それではここからは実際におもちゃ名をあげていこうと思う。
まずは「ハマらなかったおもちゃ」から。
その前にしっかり伝えておきたいのは、決してこれからあげるおもちゃが悪かったわけでも、
息子が悪かったわけでも、ましてやMさんが悪かったという話でもないということ。
これはあくまで、合うか・合わないかの相性の問題。
たしかに、せっかく買ったのに息子が実際に遊んだのはほんの数分。
あっという間に興味をなくして、ほとんど出番がないまま終わってしまい
当時は悲しく、ちょっとした苛立ちも覚えた(笑)
でも今振り返ってみると、息子の特性や成長段階に合わなかっただけなのだと思う。
だから、どんなふうに合わなかったのかも含めて紹介してきたい。
ちなみに、息子の特性はざっくりこんな感じ
• 完全な自由より「ある程度のルールや完成形」があった方が取り組みやすい
• ゼロから創作するより「誰かの作った世界を体験し、自分なりに膨らませる」のが好き
• 遊びに“意味”や“ストーリー”があると興味が続くタイプ
遊ばなかったおもちゃたち
① BRIOビルダー
→ 想像して自由に組み立てるのが前提のおもちゃ
息子は、作りたいもののイメージがはっきりないと手が止まってしまうタイプ。
完成形が想像しづらく「何を作ってもいいよ」という“自由なスタンス”が、かえってピンとこなかったのだと思う。
「何かを生み出す」より、「作られた世界を味わう」方が好きな息子には、自由度が高すぎたのかもしれない。
⸻
② ジスター
→ 構成要素が抽象的で、想像力に委ねられる
ジスターも、BRIOと同じく「何を作ってもOK」なおもちゃだが、パーツがさらに抽象的で
“何ができるのか”のイメージを持ちにくかったようだ。
息子にとっては「自由=方向がない」になってしまい、どう関わっていいかわからなかったのかもしれない。
⸻
③ プラントイ ビーハイプ
→ 色合わせやバランス感覚が求められる知育系おもちゃ
構造的が美しくて、チのキャラクターもかわいいらしい。
もしかすると今なら、ハチと会話してごっこ遊びがはじまったかもしれない。
けれど、当時は“ハチが何者か”“なぜこれをするのか”といった背景が感じられず、入り込めなかったようだ。
⸻
④ プラントイ ソート&カウントカップ
→ 分類・数を扱う知育要素が強い遊び
息子はもともと数字に強く、当時すでに100まで数えられていた。
そのため「カウントして数の概念を学ぶ」段階はすでに過ぎており、
「色を分けしよう」「並べてみよう」という遊びにもあまり興味を示さなかった。
⸻
⑤ HABA ペグ刺し
→ 型に合わせてペグをさすシンプルな操作遊び
息子は手先は器用だが「意味のない繰り返し作業」には乗ってこないタイプ。
ペグを刺す行為そのものに“目的”や“物語”が感じられなかったらしく、すぐ飽きてしまった。
とはいえ、トミカと組み合わせて電柱に見立てるなど、自分なりの意味づけをしてちょっとだけ遊んではいた。
⸻

今振り返ると、息子が遊ばなかったのは「そのおもちゃのアプローチと、息子の“心が動くポイント”がちょっとずれていた」だけなんだよね。
『なんでMさんの息子さんみたいにキレイに色分けして並べないの』とかイラだっていた、あの頃の自分にチョップしたい。
ハマったのは、息子を遊びを観察して選んだおもちゃ
ここからは、ハマったおもちゃを紹介していきたい。
ただ、まず大前提として伝えておきたいのは――
息子にとっては、すべての遊びの中心に“トミカ”があるということ。
だからこそ、ここで紹介するおもちゃはどれも、トミカ遊びをもっと楽しむための“拡張アイテム”のような存在。
正直、トミカに興味がない方にとっては、まったく参考にならない情報かもしれない。
「ここまで読んできてそれ言う?」と思われるかもしれないけれど(笑)
できれば最後まで読んでもらえたらうれしい。
⸻
① Waytoplay
→ トミカと組み合わせる“道”。レイアウトの自由度が高く、遊びが広がる。
最初は道路が描かれたプレイマットを使っていたが、
自分で道をつなげたがる様子があったので、当時一番大きなセットを購入。
柔軟性があるため、坂道にも対応できるし、ゴム製なので汚れてもサッと拭けて管理も楽。
この道路が加わったことで、トミカの世界は一気に広がった。
もはや“息子のおもちゃを語る上で欠かせない存在”。
⸻
② グリムス レインボーフレンズ
→ 人が加わることで、トミカの街に“暮らし”が生まれる。
実はこれもMさんの影響で取り入れたもののひとつ。
カラフルな車とのセットで購入したが、実際に使われたのは人形のほうだけだった。
無印良品の棚に整列されている姿もかわいらしく、出番も多かった。
⸻
③ シュライヒのフィギュア
→ 動物が加わることで、街のスケールがぐっと広がる。
動物たちが加わることで、トミカの舞台は街中から自然の中へ。
動物園、牧場、ジャングル探検、さらには戦いごっこまで…
物語のバリエーションがどんどん増えていった。
⸻
④ ラドガグレのフォレスト
→ 街の背景や“舞台”として遊びを支える存在。
これはいわゆる“遊びの土台”。
自然の多い北海道で暮らしていることもあって、木々の存在は息子にとっても身近。
動物を置いたり、建物の背景として並べたり、想像の世界を支える大切なピースになった。
⸻
⑤ ルブロナ タウンセット
→ ようやく出会えた「街にちょうどいいカタチ」。
トミカには“トミカタウン”というシリーズがあるけれど、
意外と“普通の家”や“街並みっぽい建物”って少ない。
積み木で代用しようとしたこともあったが、崩れるたびに遊びが中断されてしまい、
それにイライラしてしまう息子の姿をよく見ていた。
そんなときに出会ったのがルブロナ。
トミカとの相性もよく、丈夫で扱いやすく、なにより見た目がかわいい。
“見た目重視”な私も大満足の逸品だった。
⸻

こうして振り返ってみると、息子は私がどんなおもちゃを与えても、
最終的には自分の「好き」を軸に世界を広げていたように思う。
今もし「◯◯でしか遊ばない」と悩んでいるお母さんがいたら、
「それどんなにあがいても、子どもは好きなことしかしませんよ」と伝えてあげたいかも(笑)
失敗から気づいた、ほんとうの“正解”
一時は、Mさんや人気インスタグラマーさんが紹介したおもちゃが“正解”だと思っていた。
憧れて、真似して、失敗して、
でも、だからこそ「息子の“好き”をちゃんと見る」ことを覚えていった。
おもちゃ選びは、息子と一緒に私も成長できた。
そんな経験だったと思う。
もちろん、情報を参考にするのは悪いことじゃない。
誰かの発信に勇気をもらうこともあるし、真似してみることで見えてくる景色もある。
今でも、素敵な投稿を見ると「これ欲しいな〜」とつい真似して買いたくなることもあるけれど、
最後に選ぶのは、やっぱり“自分の子ども”のことを一番わかっている親でありたい。
たとえ「トミカでしか遊ばない」と言われたっていい。
その“好き”を軸にして世界を広げていけば、
子どもはちゃんと自分の力で、遊びの幅を育てていく。